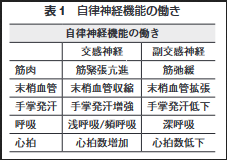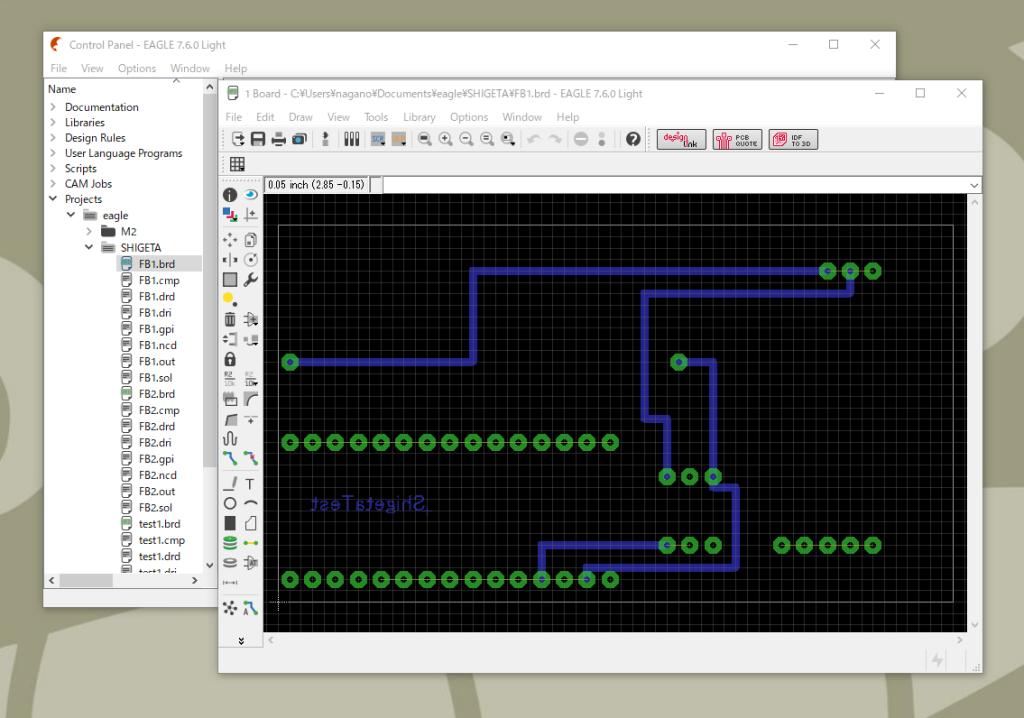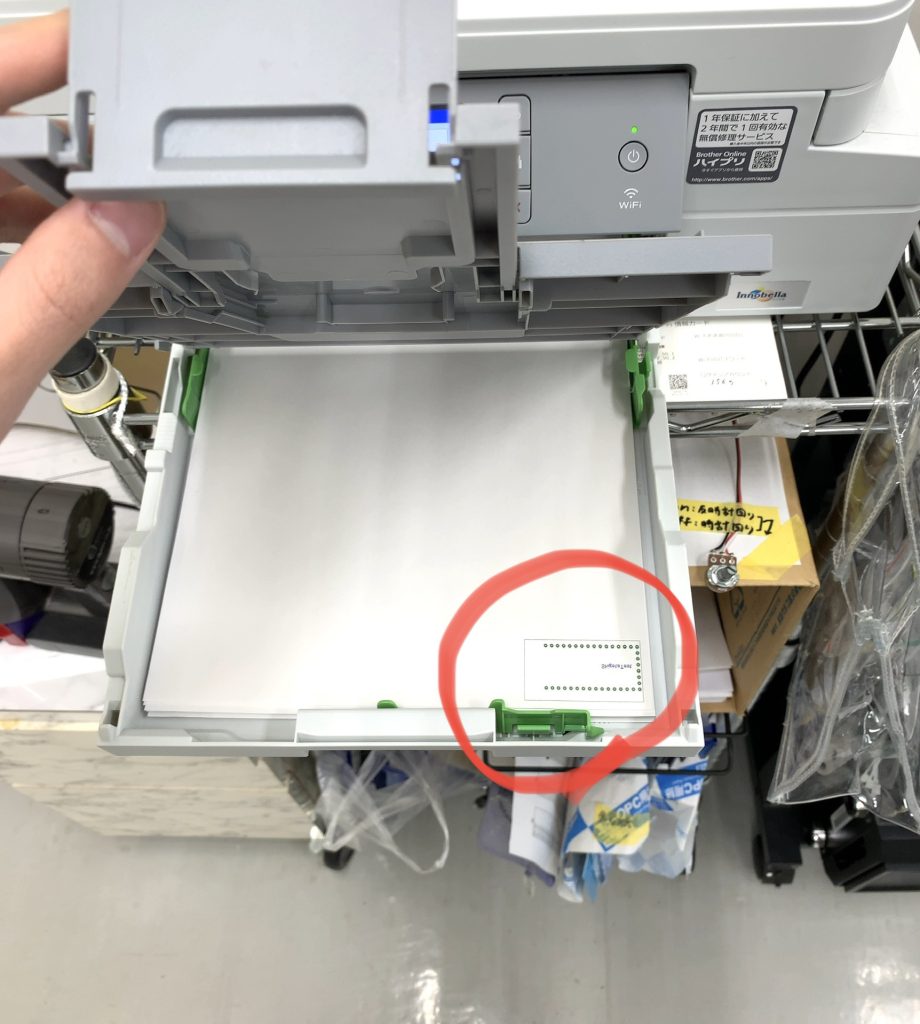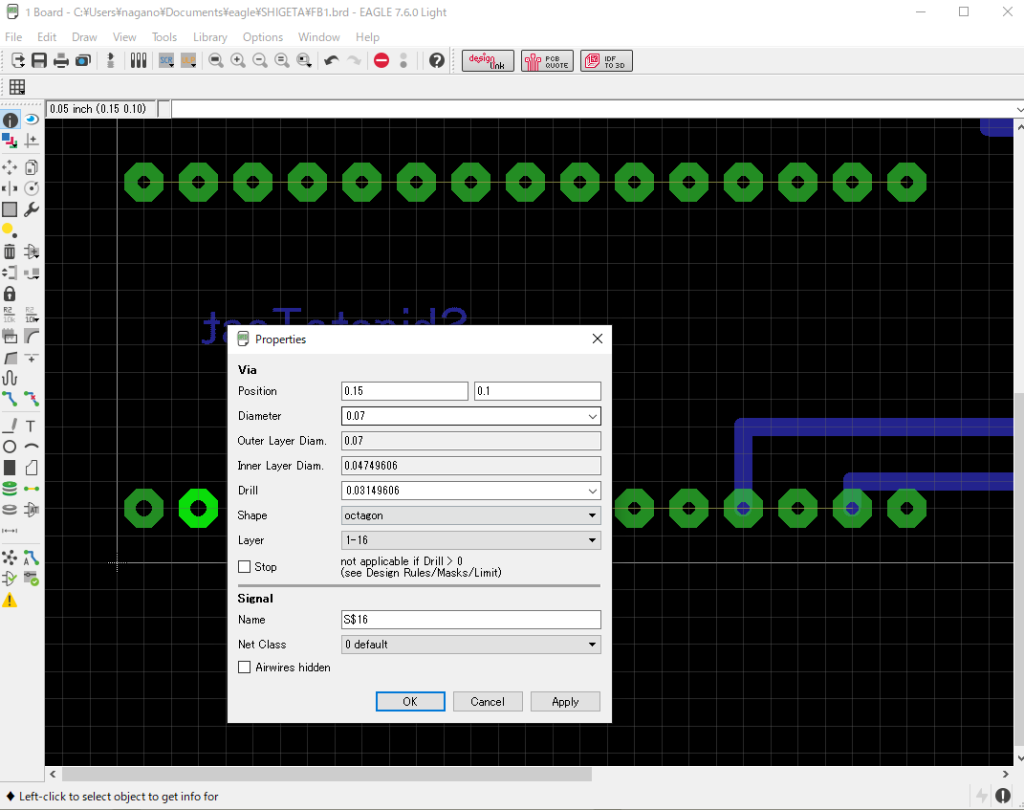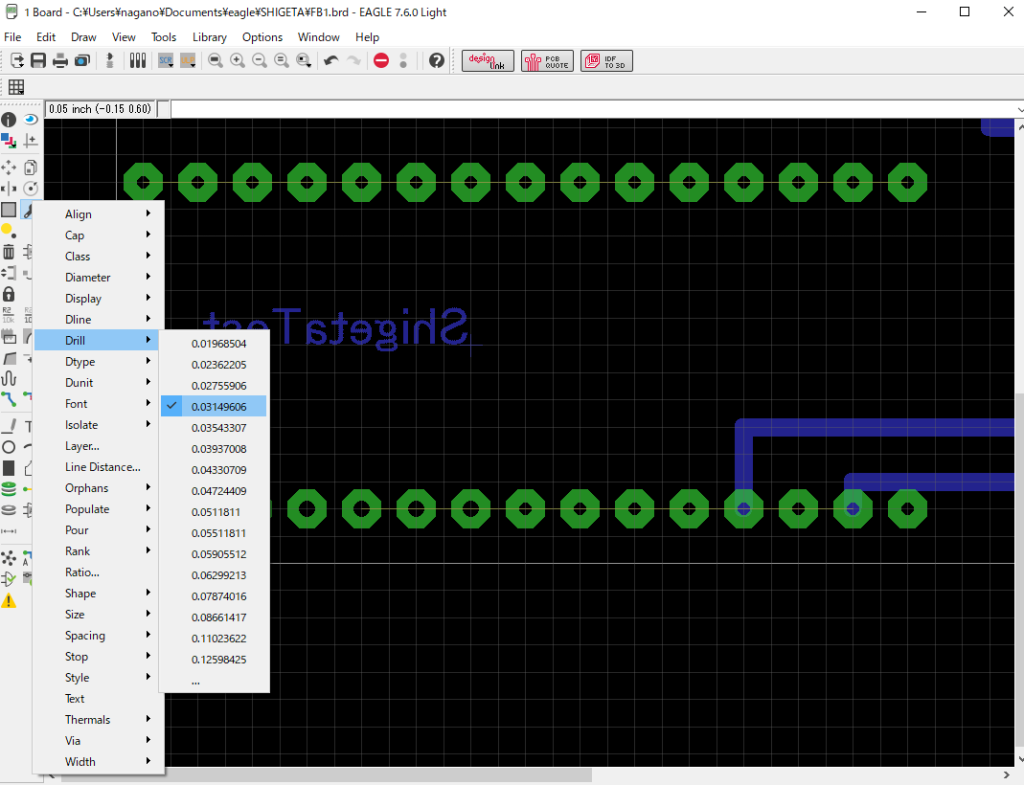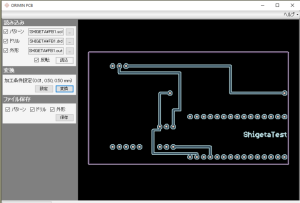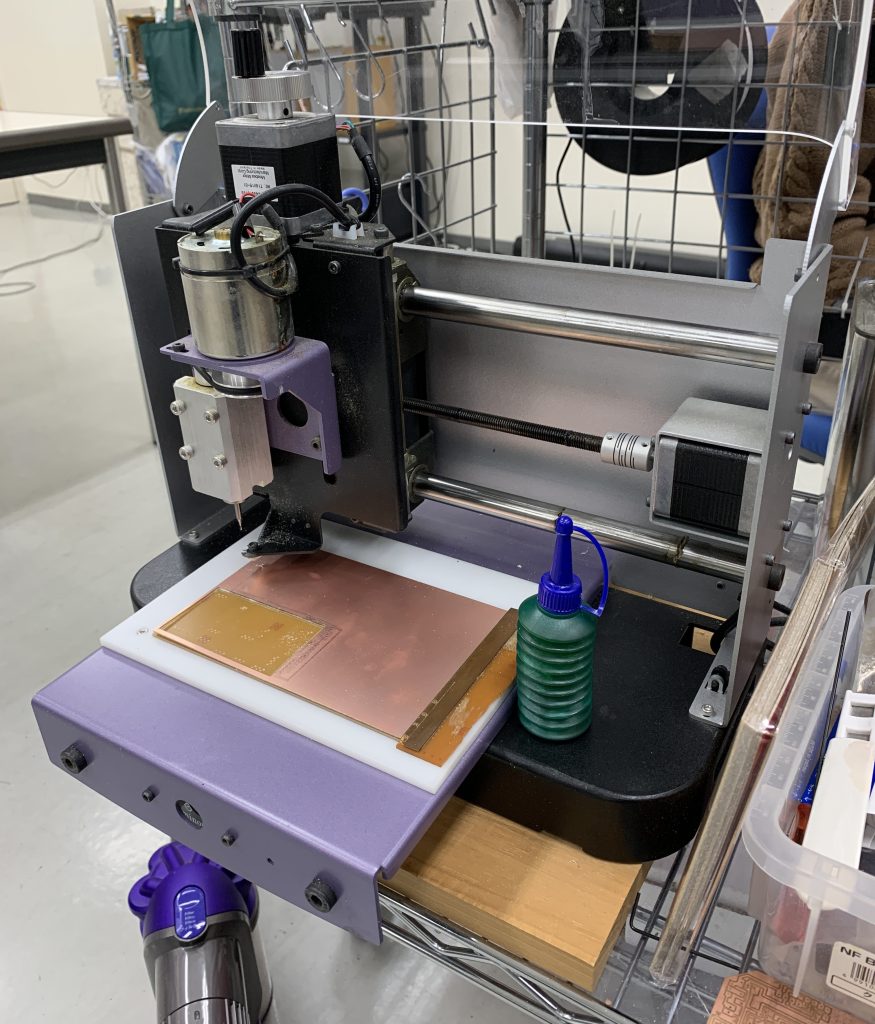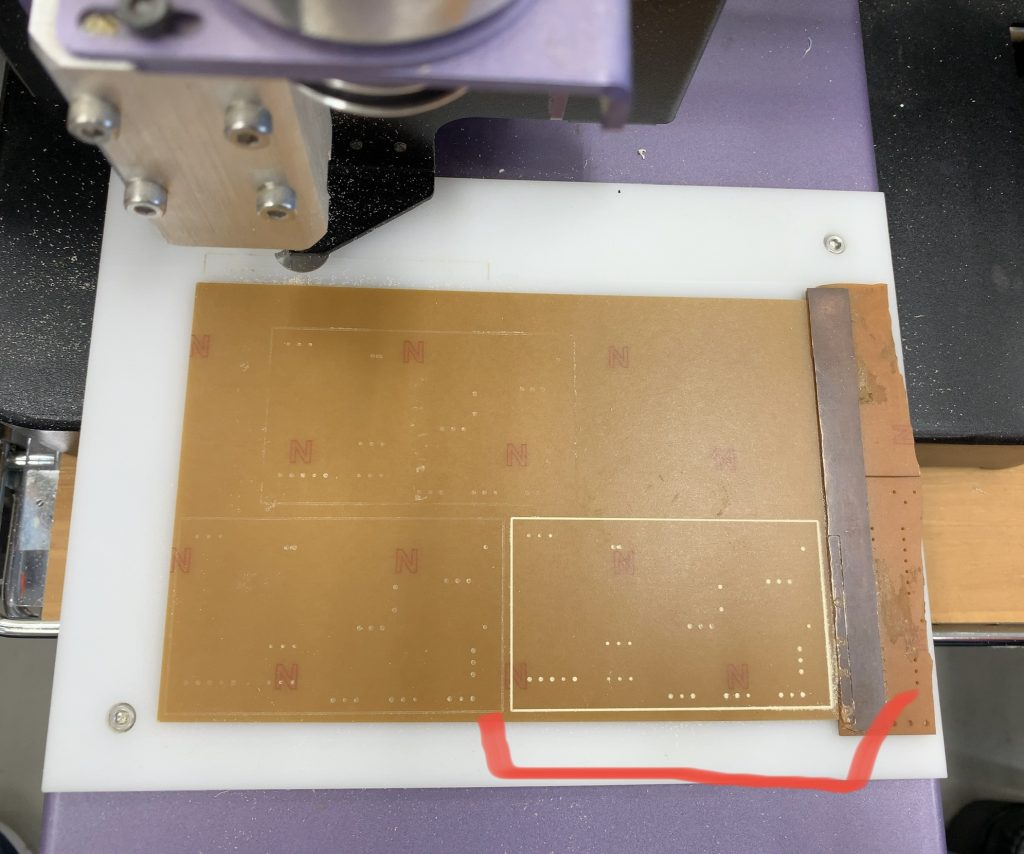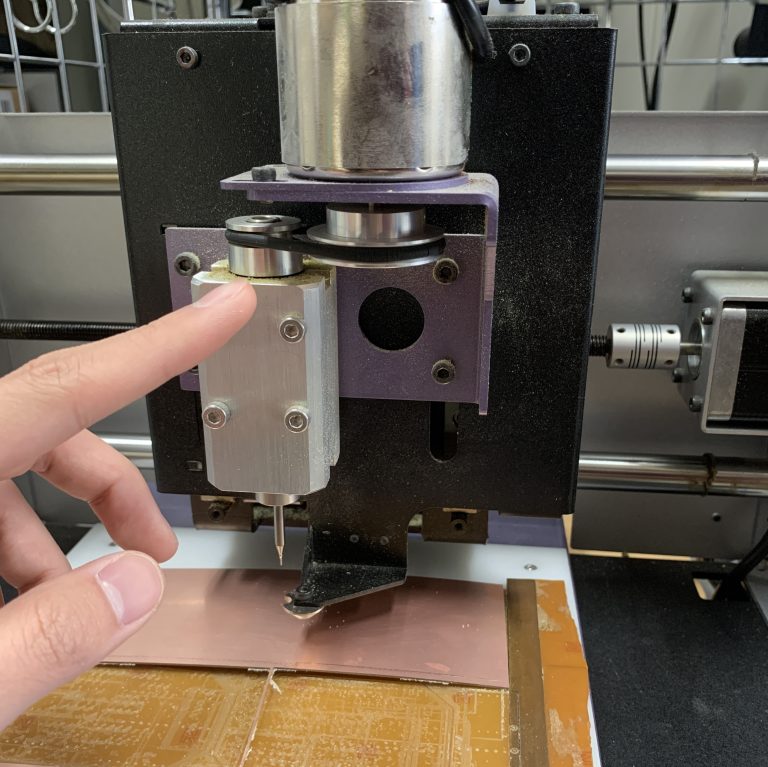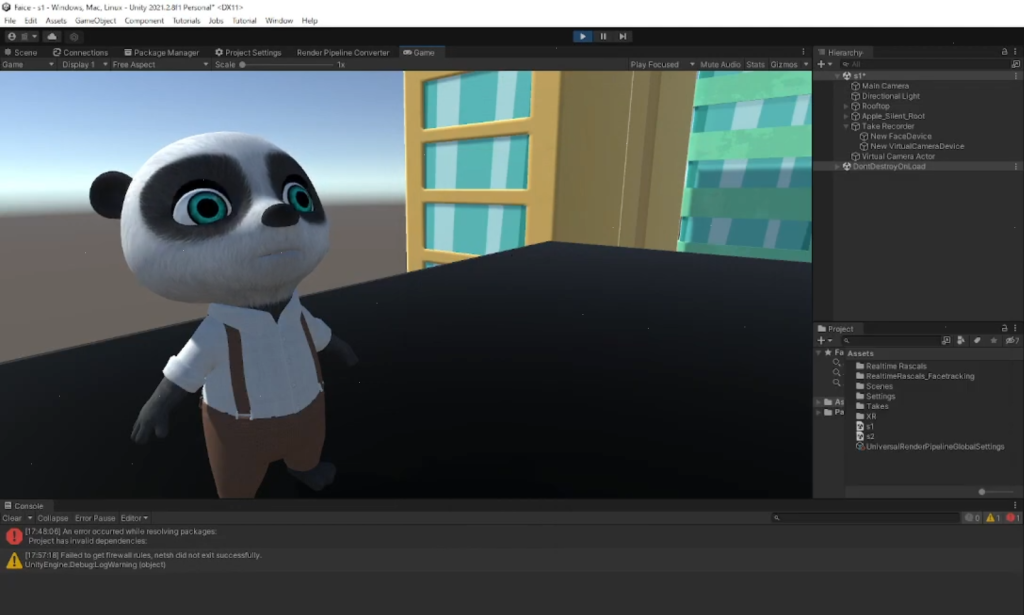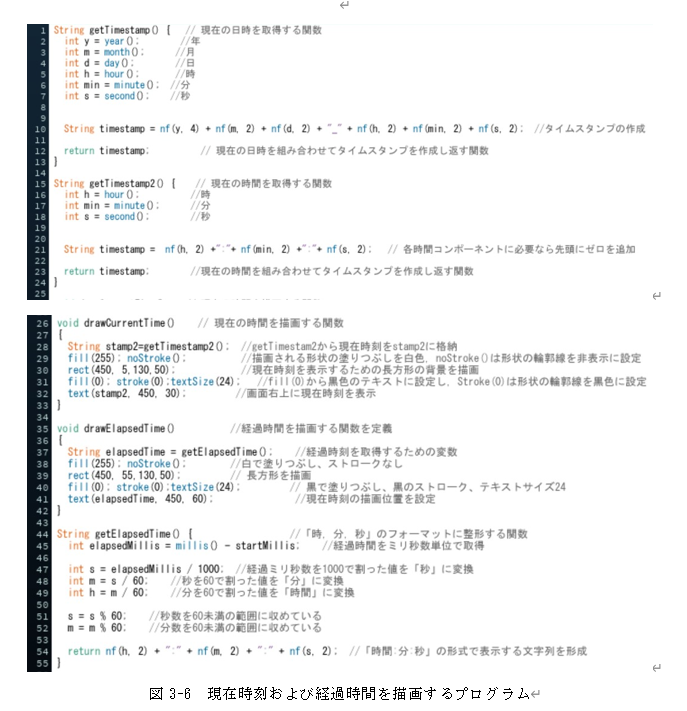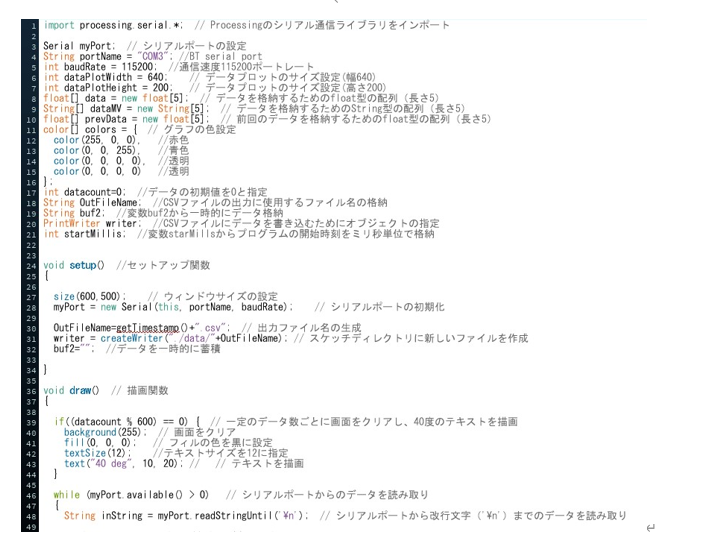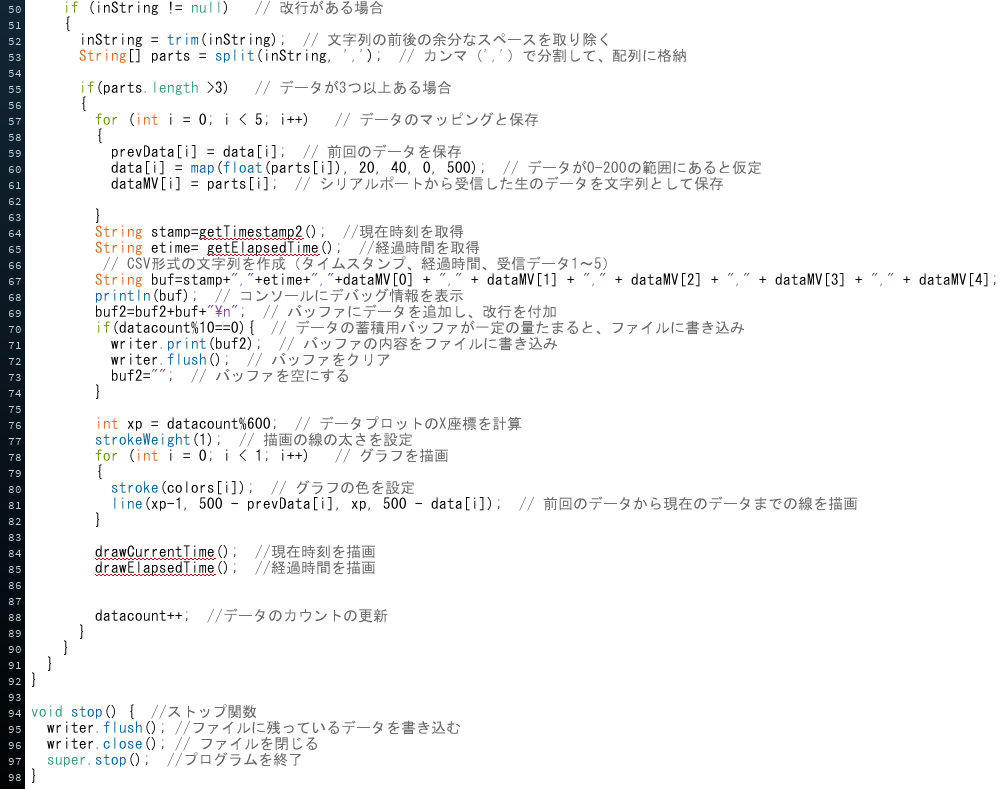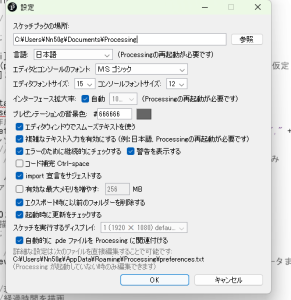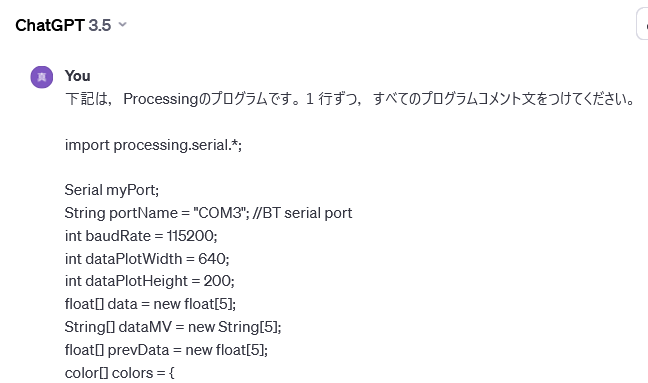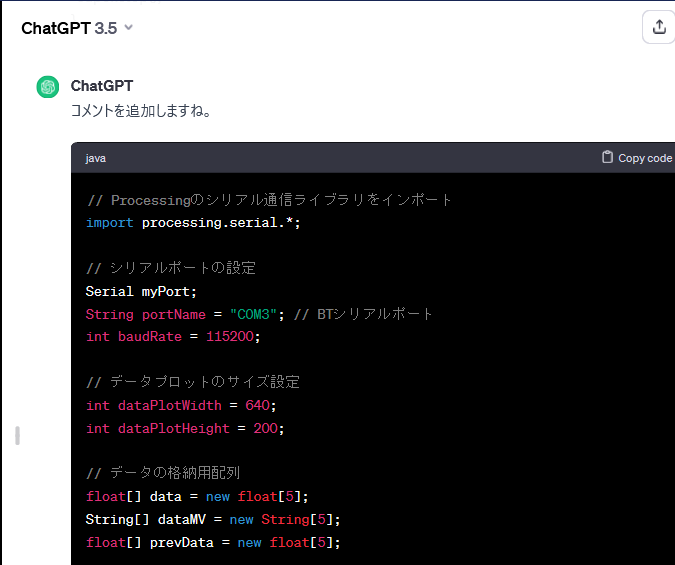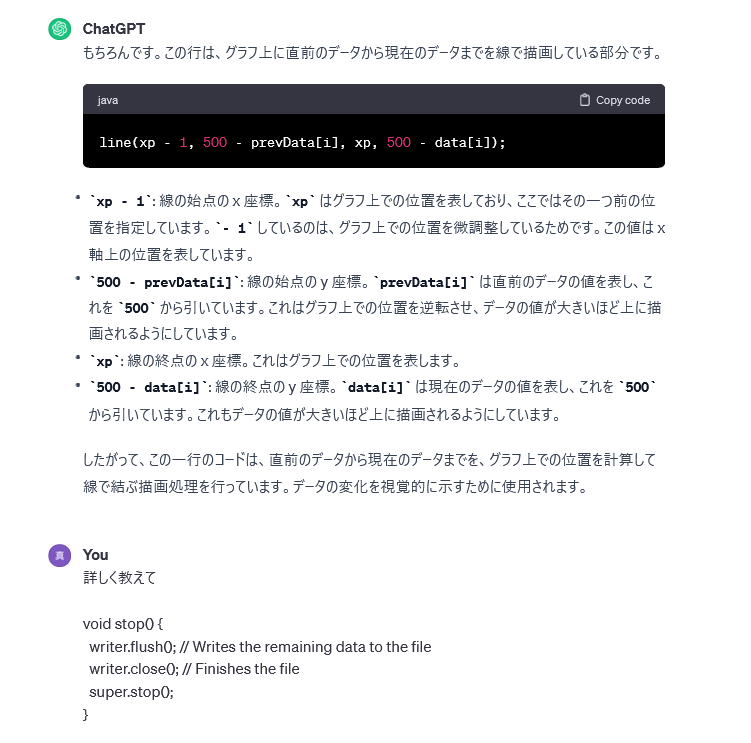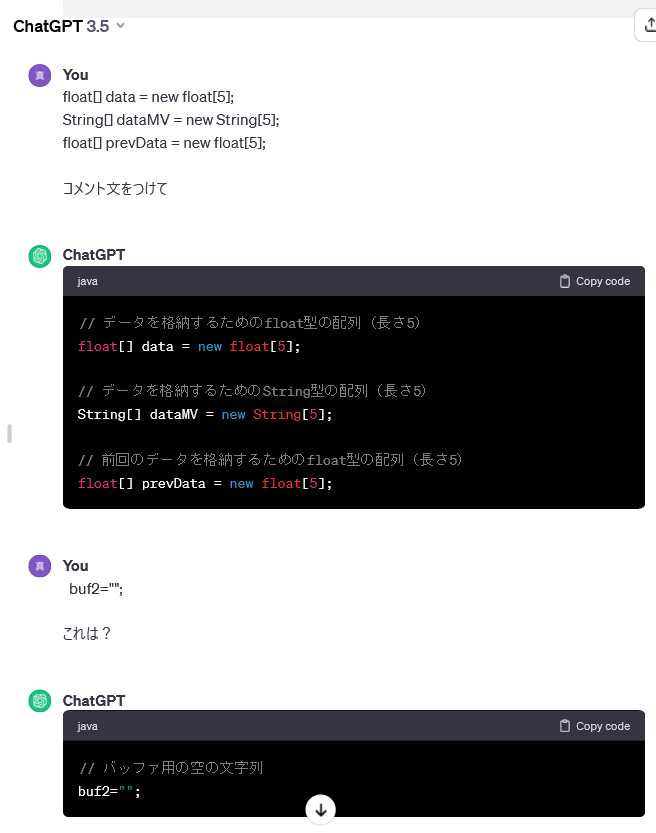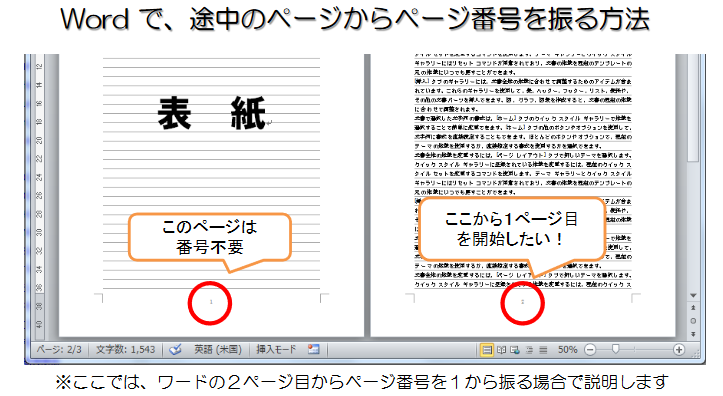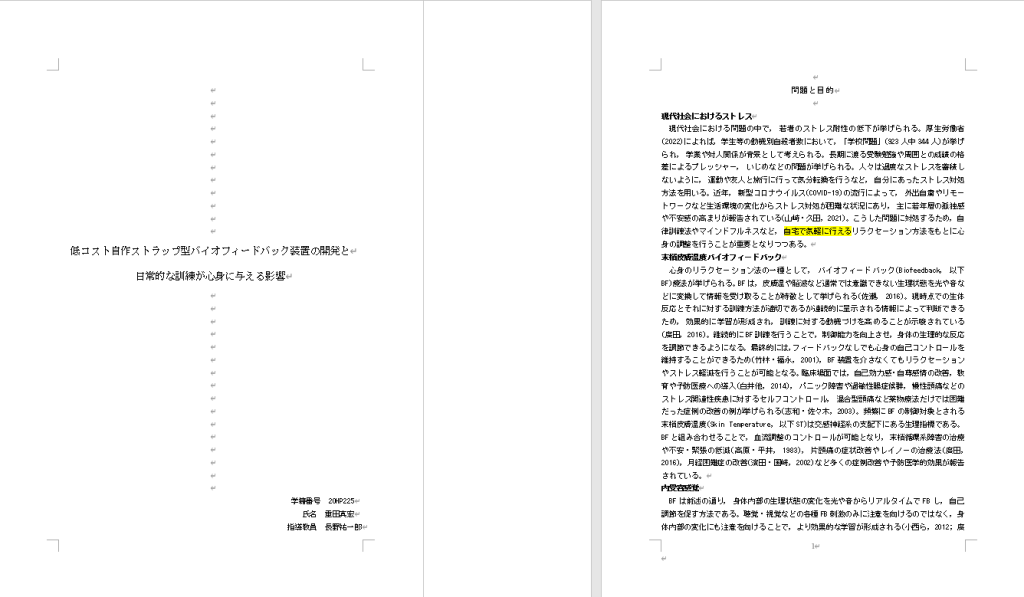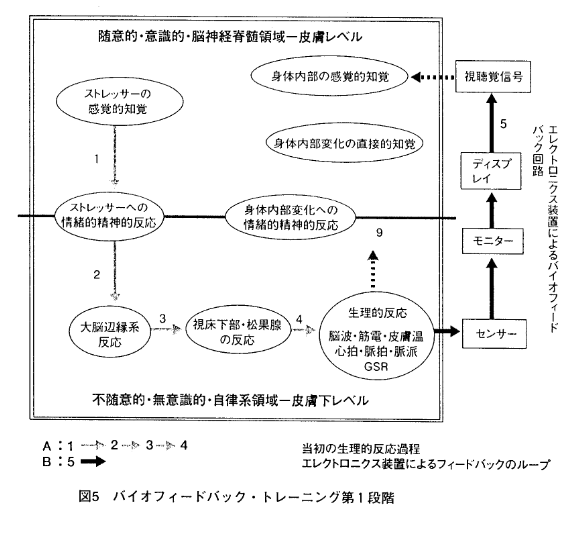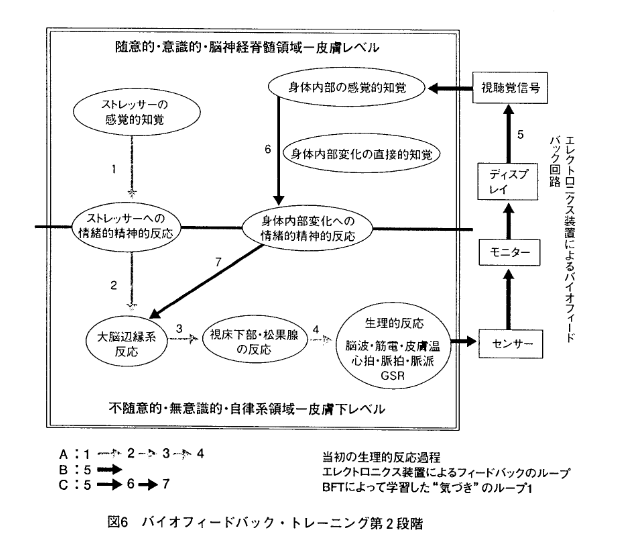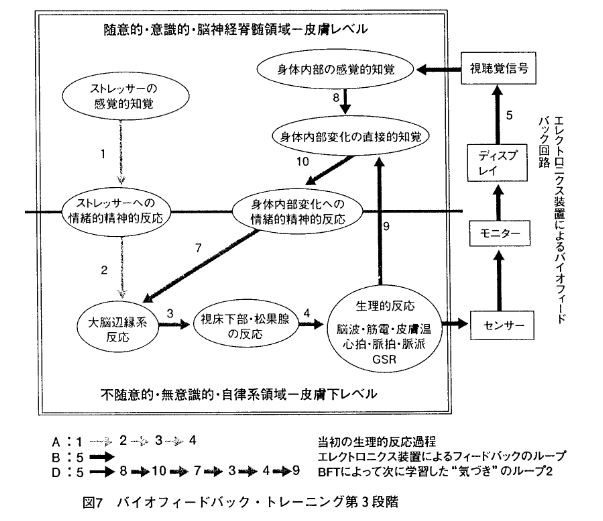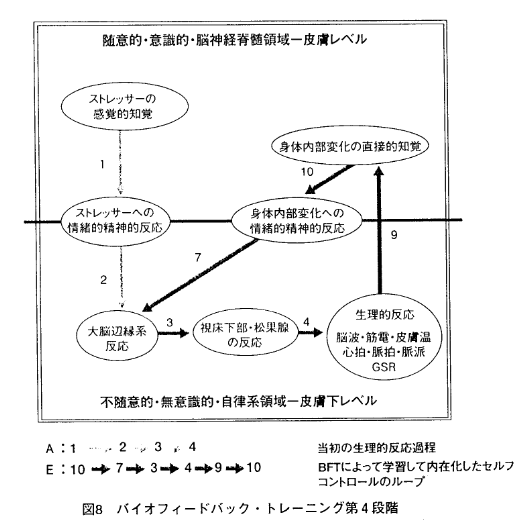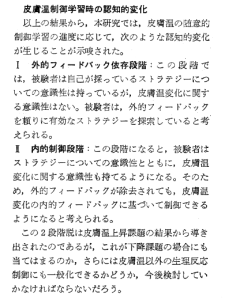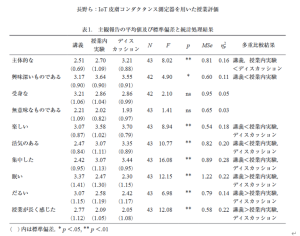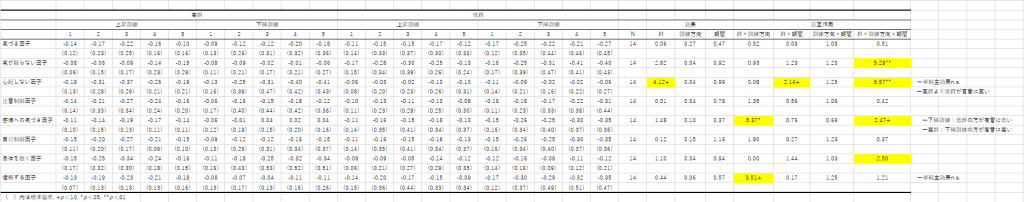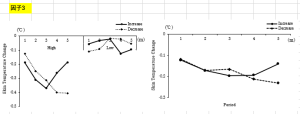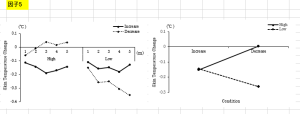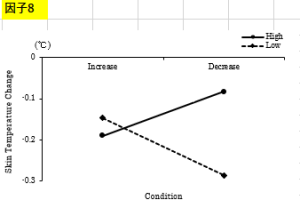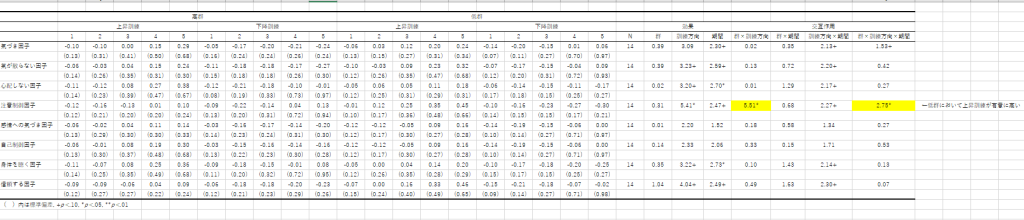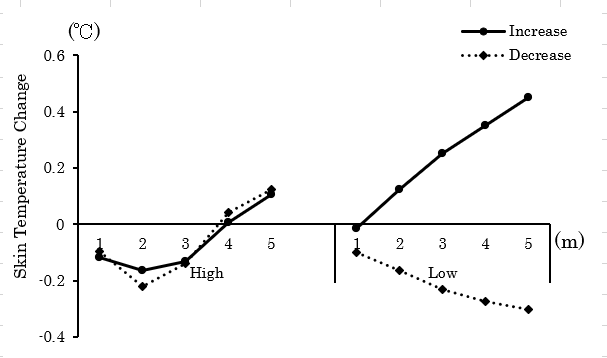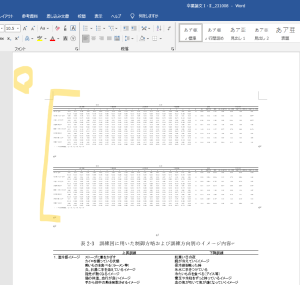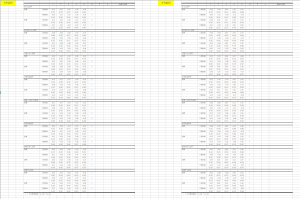生理指標の紹介_パワポ
====================================================================
1. 生理指標
・心拍数(Heart Rate,以下HR):闘争逃走反応, 注意
・皮膚コンダクタンス(Skin Conductance,以下SC):感情やストレス
2. 計測機
・HR:Polar Unite→腕時計型の計測機
・SC単一::長野他(2019).の自作測定器
3. 測定方法
①HR
・HR:PolarFlowソフトのインストールは,こちらをクリック。
・取り扱いガイドは,こちらをクリック。
PolarのIDとパスワード
・Polarアカウント→・bunpolar01~05
・Googleアカウント→bunpolar01~05@gmail.com
・Polar、Googleアカウントのパスワード→bgu3568533
②SC
・SCの計測リンクは,こちらをクリック。
4. 充電方法
・HR:Anker製のアダプタに指す→モニタに100%と表示されれば完了
番号が書いてないのはとらない。
・SC:円型の充電器に指す→中央の明りが消えれば充電完了
*計測機の充電が切れるのが早いため,前日もしくは当日に充電する。
SCは予備のため三台準備
===================================================================
生理指標(HR, SC)の解説しているサイトは,こちらです。
計測体験時(お笑い動画)のSCデータを下記に添付しました。